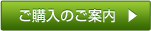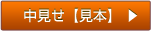勉強はどこでする?
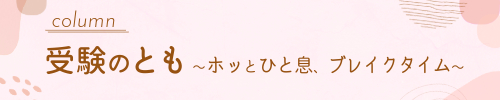

第12回:勉強はどこでする?
1日のうちで机に向かう時間がぐっと増えてくるころと思いますが
みなさんは学校、塾、図書館、自宅のリビング、自分の部屋など
どの場所が自分にとって勉強に集中できる場所でしょうか。
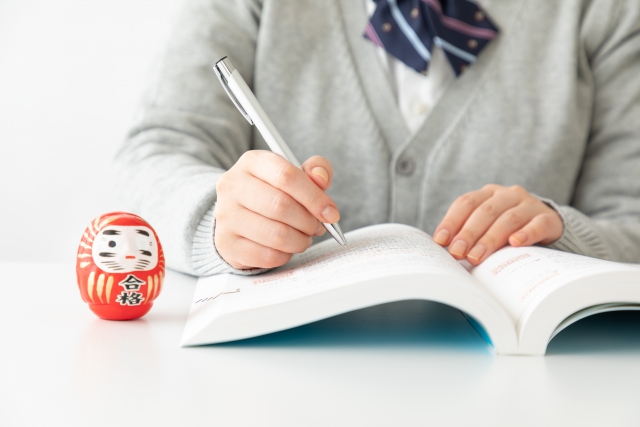
家では集中できないので、
学校や図書館、塾で遅くまで勉強してきて、家では食事をして寝るだけ、
カフェのガヤガヤしているところが意外と集中できていい、
自分の部屋にこもって机に向かうのが、一番勉強がはかどる、
など、
環境や性格、勉強の時間帯によっても、集中できる場所はさまざまかもしれません。
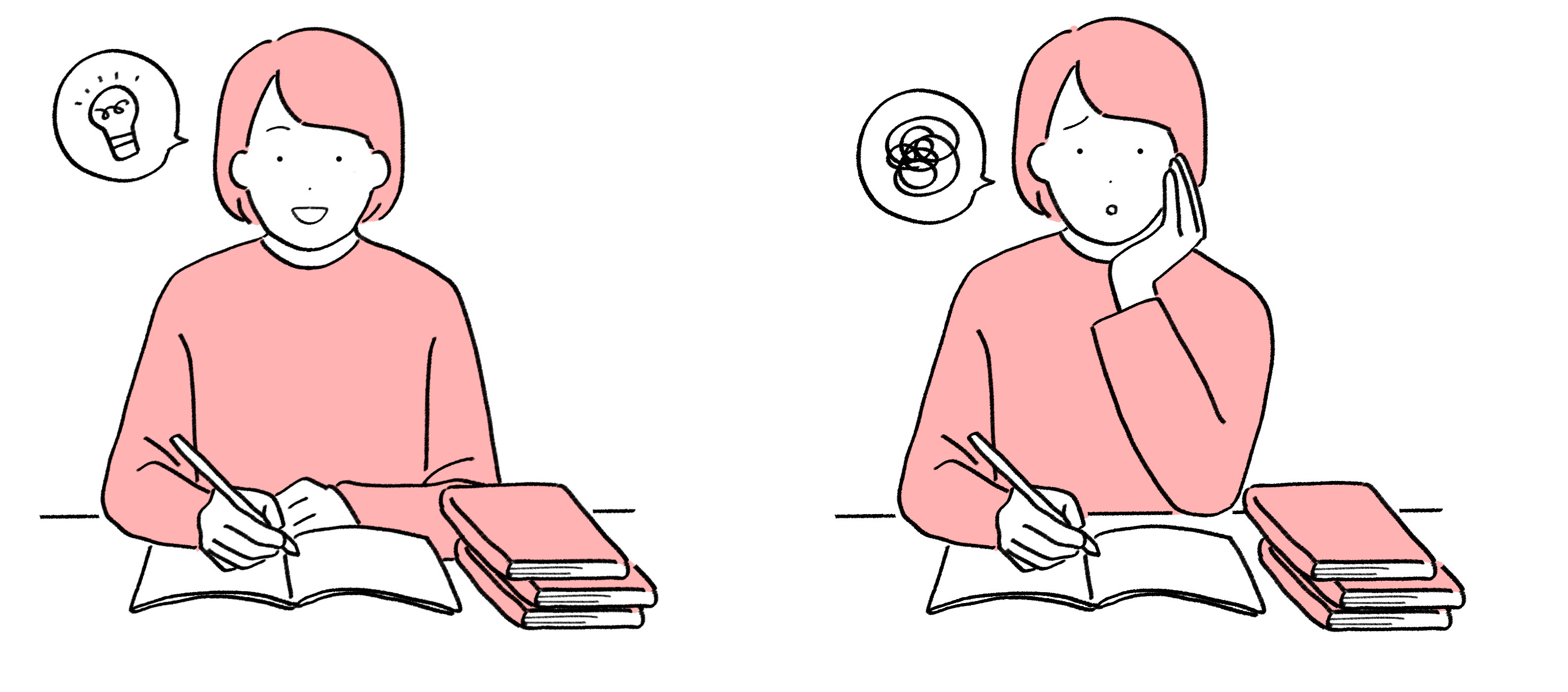
勉強のリズムがなかなか定まらないなという人は、今からでも遅くありません。
自分に向く勉強環境を見つけて、勉強への意識が高まるように心がけていきましょう。
それでもどうしても勉強習慣が身につかず、
気持ちがなかなか勉強に向かわない場合はどうしたらよいでしょうかと、
中高一貫校の教務主任経験者に聞いたところ、
「まずは子どもがその日に受けてきた授業について、親が話を聞くのがおすすめです」
と話してくれました。
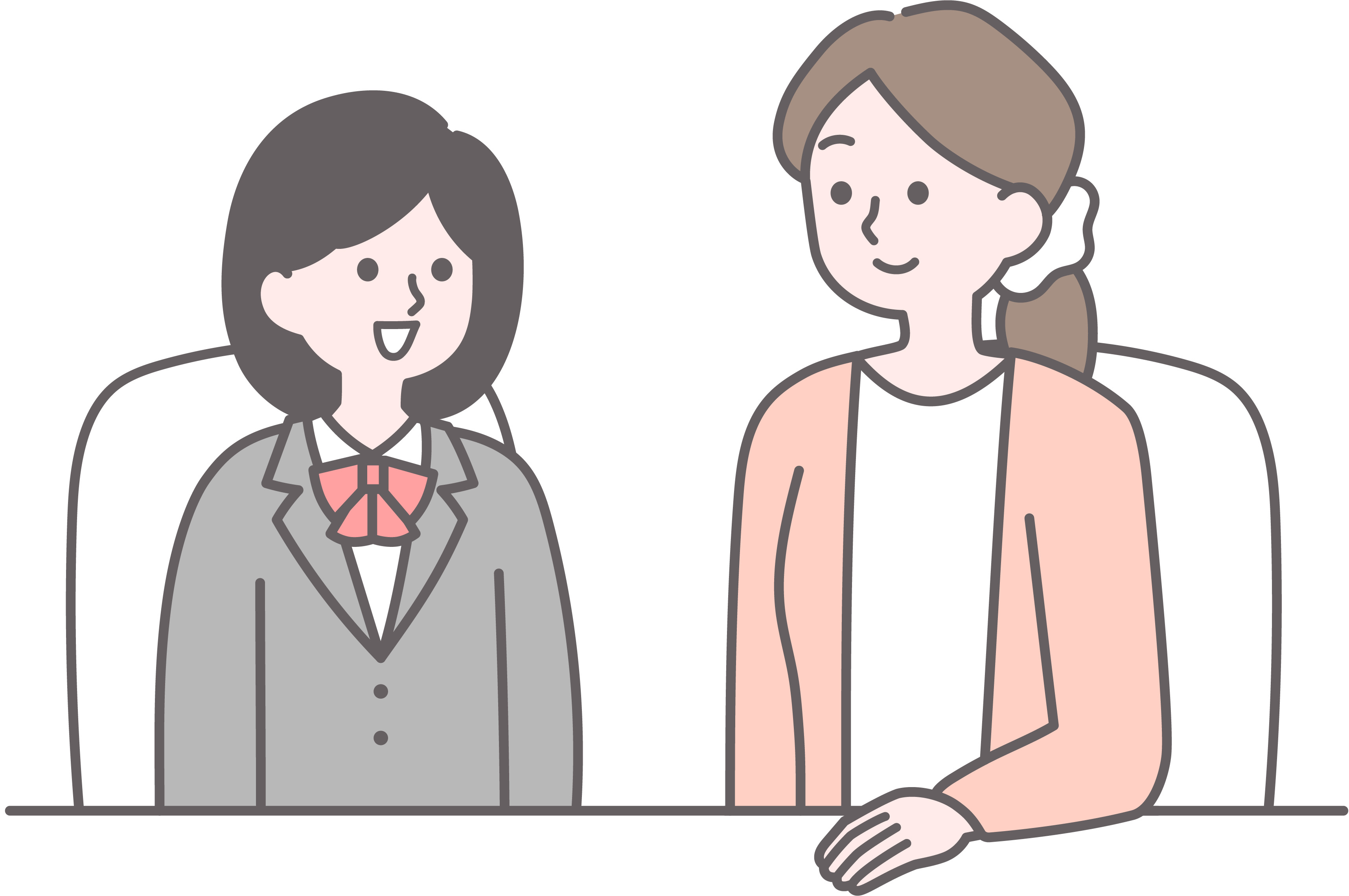
慣れないうちは好きな授業か、逆に苦手な授業についてが話しやすいとのこと。
「今日はどんなことを勉強したの?」と質問されると、
子どもは授業の内容を声に出して親に説明しなくてはなりません。
必然的にその日に受けた授業について、具体的に思い出すことになります。
そして頭のなかでポイントを整理し、
今度は自分が相手にわかりやすく解説する立場になるわけです。
この作業がとてもよい復習になり、実際に部屋にこもってノートまとめをするより、
学んだことを定着させるのに効率が良いのだそうです。
さらにこれを繰り返すことで、勉強をすることに対してポジティブな感情が生まれ、
おのずと勉強習慣も身についてきます。

もしうまく説明ができなくても、
「そんなことも説明できないの?」
「ちゃんと聞いてなかったんじゃないの?」などと
親が子を注意したり、馬鹿にしたりするのはNG。
知っている内容でも知らなかったふうの姿勢で気長に聞くのが、
子どものやる気をそがないポイントです。
ただ、子どもが、自分が理解できないのは先生のせい!
などという場合はひとまずその声に耳を傾けつつ、
「わかりにくいときは、思い切ってここがわからないって質問してみたら?」
など先生への批判ではなく、わからない部分を解決する方向に意識が向くよう、
声がけをしてみてはどうでしょう。
子どもの先生に対するジャッジが必ずしも正しいとは限らないですし、
親もいっしょになって先生の批判をすると、
子どもがますます先生を嫌うようになり、
ひいてはさらにその教科まで嫌いになってしまう可能性もあるので注意しましょう。
勉強に集中できる環境を見つけ、能動的に勉強できるようになれば、
長時間の学習習慣のリズムもつかめるようになってきます。
最初から集中して勉強に取り組める子どもはそれほど多くありません。
親子で話をしながら、
どんな環境なら気が散りにくいかなどを見つけて頑張っていきましょう。
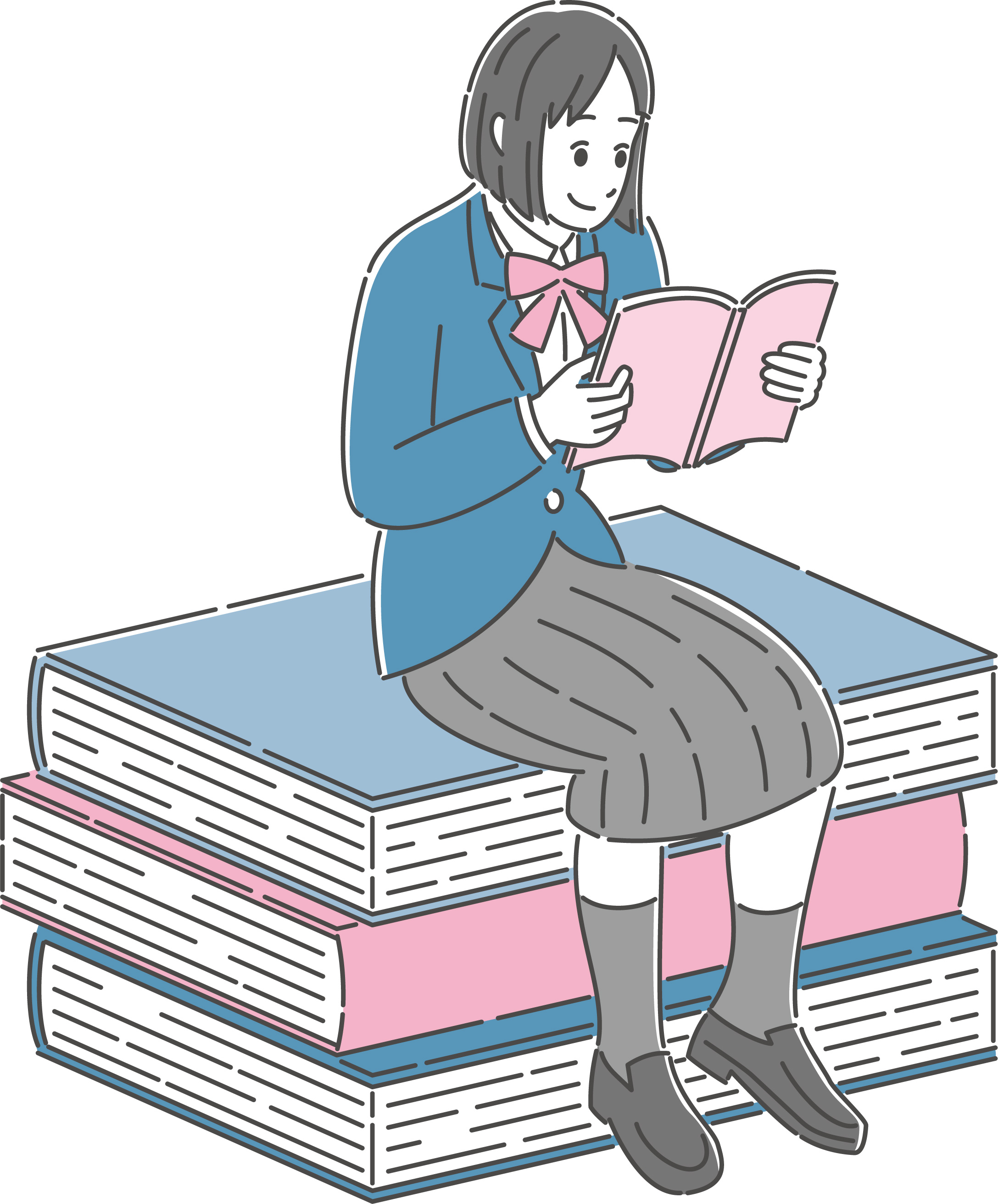
プロフィール
文/野々瀬広美
編集・ライター。生活実用の出版社3社での会社員生活ののち、フリーランスに。暮らしまわり・ハンドメイドのジャンルを中心に取材・編集・執筆などを手がける。編み物とサッカー観戦が好き。図書館司書の資格を持つ。